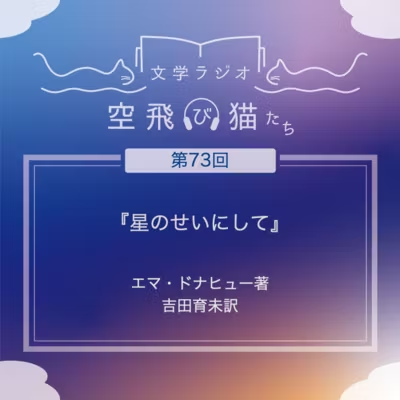【今回の紹介本】
■『星のせいにして』エマ・ドナヒュー著、吉田育未訳
今回はパンデミック小説をご紹介します。
舞台は1918年アイルランド、ダブリン。
スペイン風邪が猛威をふるう戦時下、妊婦のための隔離病棟で孤軍奮闘する看護師の視点から語られる痛切な物語。
あまりにも今のコロナの状況や世界情勢と重なる部分があり、不思議な気持ちになりました。
是非お聴きください!
【番組内で紹介したトピック】
■『星のせいにして』エマ・ドナヒュー著、吉田育未訳 河出書房新社
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309208411/
【サポーター募集します!】
Podcast番組「文学ラジオ空飛び猫たち」 のサポーターを募集しています。
案内人のダイチとミエは多くの方に海外文学を知ってもらいたいという想いがあり、ラジオでの配信を行っています。
サポーター費は月額500円。
今後の書籍代や案内役二人がイベント開催のための交通費、また我々の新たな活動費として、皆様から頂いたご支援を活用させて頂きます。
「文学ラジオ空飛び猫たち」を応援したい!という気持ちをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひサポーターになっていただけると嬉しいです。
ささやかながらサポーター特典もご用意しました!
毎週土曜日に1本のメールをお届けします。
theLetterというニュースレター配信サービスを使わせて頂いております。
こちらの有料にご登録ください。最初は無料購読登録から始まります。
Podcast「文学ラジオ空飛び猫たち」を続けていくにあたり、皆様の応援は本当に大きな励みになりますので、今後ともよろしくお願いいたします!
登録はこちらから!
https://radiocatwings.theletter.jp/
※登録されると確認メールが迷惑フォルダに入ってしまう可能性がございます。すべてのメールをご確認ください。
※特典のサポーターのサンプルとして「番外編第16回」をtheLetterにアクセス頂けるとお読みいただけます。
※もちろんサポーターとしてご支援頂かなくても、Podcastを聴いて頂けるだけでも本当に嬉しいです。
【文学ラジオ空飛び猫たちとは】
硬派な文学作品を楽もう!をコンセプトに文学好きの二人がゆる~く文学作品を紹介するラジオ番組です。
案内役の二人は、 東京都内で読書会を主催する「小説が好き!の会」のダイチ
京都の祇園で本の話ができるカフェを運営する「羊をめぐるカフェ」のミエ
文学のプロではない二人ですが、 お互いに好きな作品を東京と京都を繋ぎ、
読書会のようなテイストで、それぞれの視点で紹介していきます!
毎週月曜日朝7時に配信しています。
【SNSでご投稿ください】
番組の感想・リクエスト・本を読むきっかけになったなど、 #空飛び猫たち をつけて、ぜひSNSに投稿してください!
よろしくお願いします!
■twitter https://twitter.com/radiocatwings
■Instagram https://www.instagram.com/radiocatwings/?hl=ja
■Gmailでも受付中です bungakucafe.catwings@gmail.com
■ダイチ「小説家が好き!の会」
Twitter https://twitter.com/welovestory
Instagram https://www.instagram.com/booklogd/?hl=ja
■ミエ「羊をめぐるカフェ」
Twitter https://twitter.com/hitsuji_meguru