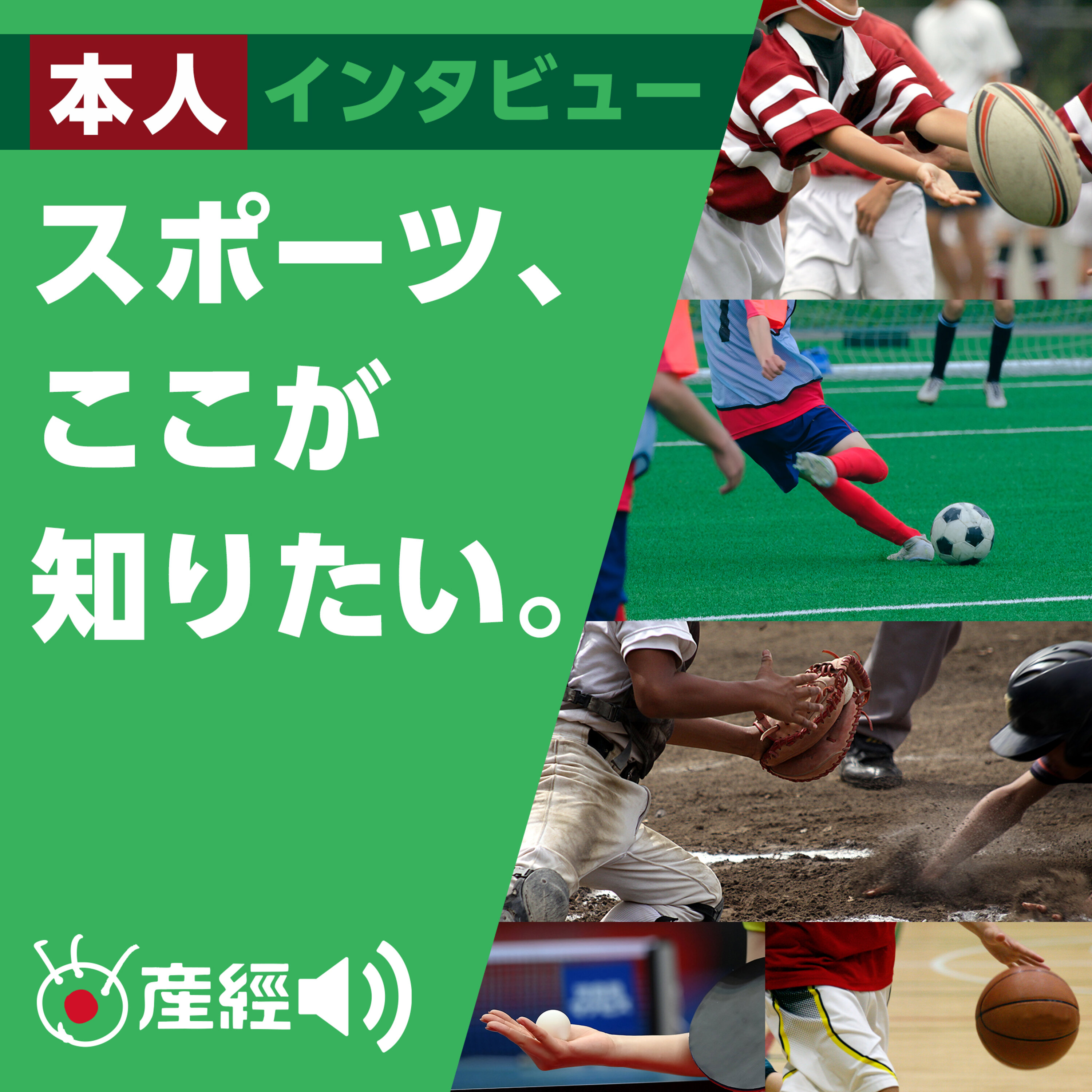トレーニングの形だけ
で言ったらあれだ、だからトレーニングされてないんだ、ビジネスマンの多くは。 何もトレーニングされてなくて、ずっと試合に行かされてるのかもしれない。
そうですね、確かに。全部アバウトに行けみたいな感じですもんね。
教育みたいなのがちゃんとやってる会社もあるけど、多くの会社は形だけっていうか、トップがこういうスキルを身につけてほしいみたいな、ポンって研修入れるけど、
現場の人は何でこの研修が入ったのかわかんないから、アバウトな練習をそれこそしてるみたいな、何かいいねって言われてるとか、何かやれって言われてる感じになっちゃうから、
研修受けて終わりとかになっちゃって、結局何も対得できてないみたいなことがよく起こってるなと思うから、結構闇が深いな。
闇が深い。
闇深いし、やっぱさすがアスリートだなと思いましたね。
そこはやっぱりこう、極限まで高めていかないと、一気に通用しなくなるみたいな話じゃないですか、厳しい世界というか。
何かそうですね、少しでもよくできることをよくしておかないと、環境とか全体的なレベル感とかっていうのは時代によって変わっていくんですよね。
でもその変わり目っていうのは読めないじゃないですか。
はい。
なのでその変わり目に対して常に対応できるように、それを何か準備を常にしているみたいな感覚ですよね。
競争の激化
それでもみんなやってんの?
結構アスリートの中でもトップアスリートの発想なんじゃないですか、どうなんですか、そうでもない?
じゃなかったら長くは続けられないと思うんですよね。
あ、そうね。
別にそれをやらなくても活躍はできると思います、ある一定の期間は。
でもその仕様が変わったり、流れが変わった時に通用しなくなる。
そうですね。
時がやっぱり来るんですよ。
確かに。やっぱり息の長い選手、そしてビジネスサマンとか経営者とかもそうですけど、そういう人ってやっぱりそういうことなんでしょうね。
常にやっぱり準備ができている。
できてる、はい。
たまたま波に乗って10日後を表す人とかもいるけど、続かないんだ。
続かないです、絶対。
なるほどね。それはいい話だな。
っていうのを、だから今36になったと思いますね。
若い時は思ってなかった。
若い時もそういうふうなマインドセットでもちろんやってたんですけど、いざこうね、自分がずっとプレイし続けていく中で、
どこが変わり目だったとか潮目だったかって結構先に進んでみないと過去のことってわかんないじゃないですか。
うんうん、あそこだったなみたいなやつですよね。
それがなんか今になってこうわかるようになってきたみたいなところはあるんで。
最近はプレイを長く続けるためにはみたいな感じのマインドセットの発信をしている感じがします、英語で。
そこを多分言語化できる人あんまりいないんですよね。
長く第一線でやってきた人にしか言語化できない。
できないじゃないですか。
しかもその中でも言語化が得意な人ってあんまりいないというか、
それを発信しようとしている人もあんまりいないって考えたら、めっちゃ希少な情報なんじゃないですか。
確かにな。
勉強になるな。
なんかね、前回少しね、いつまで続けるのかみたいな話とかもあったけど、
そういう話からやっぱ最近思うのは、
アスリートのトーターツじゃないけど、生存していくための生存競争みたいなのってすごい激しいっていうのはずっと普通の人でもイメージとして持っていると思うんだけど、
それがどんどん社会全般で起こっていってるよねって思うんで、
もちろんアスリートほど厳しくないと思うんですよ、その競争の倍率とか晴らされ方がね。
勝ち負けがそこまではっきりしてなかったりするから。
チーム数が何十チームの中でとかもあるじゃないですか。
枠がめっちゃ少ないじゃないですか。
少ないですね。慣れる人も限られてますしね。
会社にしようと思ったら何百万社かあるから。
認知能力の重要性
何百万社かどっかに引っかかればいいから。
なんかね、その競争の倍率でいうとかなり低いんだけど、
裾野が広いというか。
けど、会社も維持できなくなってくるだろうなとか、
社員であとうのリスクだよなと思っている経営者ってすごい増えてると思うから、
ちっちゃいところとかはですね。
本当に必要なところで必要なだけとか、
本当に能力のある人とか、会う人とかっていう感じで、
選ぶ基準が高まっていってるなと思うんで、
そういう意味ではね。
とか、入れたとしても条件がめちゃくちゃ悪いとかがあったりするから、
やっていけないみたいなことも起こるので、
例えばアマチュアのサッカーチームに入るとかだと生きてはいけないとかがあるじゃないですか。
そうですね。
みたいな感じで、させてはもらえるが生きてはいけないみたいなことが起こると、
生きていける水準みたいなのがどんどん上がっていって、
みんな競争に晒されてるなぁみたいなことをすごい感じますね、最近。
そして加速するだろうなぁと思ってます。
意外と競争する倍率は下がってるのかなと思ってましたけど、
意外と上がってるんですね。
あのね、競争心は下がってるけど、競争する環境が高まってるって感じ。
それだ、競争心は確かに下がってますね。
そこまで厳しいゲームになってきたときに、
しかも参加したくて参加したわけじゃなかったりするから、
そういう社会で、資本主義みたいなレベルでいくから、
別に参加したいわけじゃないけど、そこのたまたま入れられてたみたいな感じだから、
モチベーションが多分ない人はないですね、多くの人は。
だから、そのゲームの中のゲーム、
例えばその中のサッカーという種目とか、その中の何とかっていう種目っていうか、
競争するだけのとか、そこで頑張るだけの動機を見つけれたらいいけど、
ない人はね、なんか競争させられてるし、どんどんルール厳しくなると、
競争したくなくなるっていうやつなんじゃないかなと思うんですけど。
それはあるかもですね、人はあんま変化したくないですからね。
変化しなくてもいいんであれば、そのままでやっぱり行きたいですし。
でも、やっぱりサッカーで言ったら、戦術をいかにして体現できるかっていうところなんで、
個人で言ったら体験できる運動能力だったり、技術だったり、知能を持ってるかなので、
その戦術が複雑になればなるほど、やっぱり求められる能力って増えるじゃないですか。
できなきゃいけない。それにやっぱり対応していけない選手っていうのがやっぱり淘汰されていってしまうような気がしますね。
結局アメリカ人とかだとやっぱりスピードがあって、縦には速いけどそれ以外が何もできないみたいな。
サッカー知能的にもやっぱり低いことが多かったりするんで、
運動能力だけで何でも解決できてしまってきてから、大学卒業するまでそういうことを別に覚えなくてもよかったんですよね。
でもプロの世界に入るとそういうわけにはいかないっていう事実を突きつけられて、消えていってしまう人が多い気がします。
11人がね、相手の人数もいると22人が同時に動いてるみたいなことを思うとね、そういった理解がないと身体能力だけではどうしようもないですよね。
はい、そうなんですよ。それがお出かけ入れ切れない人とかを見てるとイラッとするんですよね。
せめてね、その重要性を分かって、分かっていないことは自覚してほしいですよね。
学ぼうという姿勢というか、私はこれまで身体能力だけでやってきたけども、戦術を学ばなければならないって言ってくれたらね、一緒に考えられるけど、できてると思われるとちょっとね、契約切れてほしいなと思っちゃいますよね。
言っちゃダメ、それは。
一緒にやるね、みんなも大変ですもんね。
そうなんですよ。いったってもう認知スポーツですからね、認知。
もうこの社会、認知が重要ですよ、むちゃくちゃ。もう本当仕事でも何かスキルがあるか云々の前に、認知能力が低いと。
そこなんですよ。
コミュニケーションができないし、連携ができないから。
できないですね。
チームの一員としてね、いればチームにマイナスになっていくみたいなことが起こって、恐ろしいことです。いない方がいいっていうのは結構恐ろしいことなんですよね。
まさにそうです。
それはスキルよりも多分認知能力の方が影響していると思う。
そこですね。
スキルなくても使いどころだったりするじゃないですか。
はい。
だから、あるところをうまく使えばいいけど、その連携を理解できないとか、何が言われているかが理解できないという状況になっちゃうと、どうしてもいることがマイナスになってしまうので。
なっちゃうんですよね。
排除されちゃうみたいな、合理的に考えたら排除されてしまうみたいな。
恐ろしいですよね。しかも認知能力が低いと。
分かると思うんですけど、意識次第ですけど。
意識でどうにかなるのかな。
どうなんだろう。私は子供の時から認知能力が高い気がするんですけど、
それを自分が持っていないようにして、
それを自分が持っていないようにして、
自分が自分が持っていないようにして、
自分が持っていないようにして、
認知能力と運動能力
でどうにかなるのかな どうなんだろう私は子供の時から認知力は高かったのであろうか
いうのがわからないですよね なんか認知能力がみんな多分最初そこまで高くなくて成長していく
その では体が大きくなるのと同じように認知能力が高まっていくけどある人は止まっちゃう
みたいなやつなんじゃないか 止まってから伸びが悪くなるみたいな 身長が伸びなくなるみたいな人で
身長何十センチから100…小さい人でも140センチぐらいはあると思うんですけど身長 140センチぐらいまでは伸びるけど病気とかじゃなかったら
けどもう伸びないみたいなのがあった人じゃん身長とかって なんかあれに近いのかなとかって全くあれですよ何の根拠もないですよ
僕の見てきた感じでいくと何回どのように伝えてもどのような経験をしても 認知がここ全然できないなぁみたいな人とか見てると
これは どうしたらいいんだろうと思う時があるんですよ
世代とかもありますか 世代?
世代間の違いみたいなその認知力 あー
そういうのもあるけどそれとちょっと認知というよりは何かね価値観でそれを書き換えれる 柔軟性みたいなことの方で言ってるかもしれない
とか同時に見れるとかその世代の人ってこのような価値観を持ちがちだけども 僕たちはこのような価値観を持ちがち
だけれどもみたいなことを一旦置いてみれるみたいな もう少しそうですねその大きい意味でのって意味ですね
あのビッグピクチャー
っていうのもあるけど小さいのもあると思います個人レベルでもなんていうのかな 例えば
何があるかな 12回ぐらい言ったことを全く覚えてないとか
それって認知なんですか 記憶力もあるけど例えば言われてる時にそれを言われていると思っていないとかっていうのはその時の記憶力じゃないけど理解力にもなるのかな
し周りの人が何だろうなこうオーバーラップしてきてるみたいなのが視野に入ってないとかっていうのもそうかもしれないし
いやこれ来てんじゃんみたいな毎回言ってんじゃんみたいなこの時こういうはずに 追い越していくからって言ってんじゃんみたいなのを
見えてなかったとかも結構ある 見えてないじゃなくて言ってるし見えてほしいしみたいななんかあるじゃないですか
なるほどそれで言ったら自分とボールしか認知できない人が多いんですよ
でもサッカーって相手も味方もいるしスペースもあるし たくさんのことを認知しなきゃいけないです同時に
それができないと成り立たないスポーツなんですけど アメリカでプレーをしていると自分とボールしか認知できないっていう人が本当に多いなって感じるんです
これは国民性とかもあるんでしょうかね そもそもにして何かその味方の動きとかを認知しようとしないとかスペースにどこにあるのかを認知しようとしない
なるほどね 自分とボールの関係性だけで完結してしまうみたいな
シャットダウンみたいな なるほど面白い
状態です それはだから今度あれですね人間的な人間の機能としての認知能力っていうよりは確かに社会的に文化的に埋め込まれた認知能力な気もしますよね
そのように物を見てしまうみたいなのもあるのかもしれないですね
そんな気がするんですよ 確かにな面白い
ってなると肯定的に獲得するものもあると思いますよね そうじゃない人もいるんで
そうじゃない人っていうのは運動能力に恵まれていない人です
運動能力だけで解決できないから違う方法
やっぱり手段を選ばなきゃいけないっていうのは多分そこに行き着いてるんでしょうね
なるほどねやっぱり サバンナですねやっぱり生存するということにフォーカスした時に初めて開花する
自分なりの生存戦略みたいなので開花していくみたいなのがあるかもしれないですね そうだと思います
運動能力が高い人ほどやっぱりその 認知力が低いというか自分とボールで完結みたいな感じですか
なるほどね そのレベルの人たちはその身体能力がもはや
世界レベルを本当にプレイヤーとして目指すっていう資産の高さを持たないと
その生存に対するこうあれが働かないでしょ 働かないと思います通用しちゃってるからねその身体なんで
世界レベル見たらその身体能力とかだけじゃなくてみたいなスペースがあってなんとか全体を
そういう認知能力みたいなところも基準に達してないと通用しないよみたいなことは
サッカーや野球における認知の重要性
なんかねその意識を持たないとですね そこなんですよね
言葉掛けでしたね 全然違う話してる
まあいいじゃないですかこれがね こんな感じでいきたいと思いますので
言葉掛けの重要性はなんかすごく序盤でわかりました
そしてそれがスポーツみたいな時間がない中で伝えるときにグッチョみたいな一言でも基準を示していく重要な声掛けになるから
なんか安易に言っちゃダメだなって思いましたね そういう
一瞬で伝えないといけないみたいなやつになる 安易に言わないでください本当に指導者の皆さん
それはちょっと意識したほうがいいかもしれない 今ってやっぱね僕が言ったみたいなパターンって結構多いと思うんですよ
あんまり否定せずにやったらいいよって言って 致命的なやつとか大事なやつだけはしっかり評価する
みたいな使い分けをする人って多いと思うんですけど スポーツでそれはね
そう簡単にできないなって思いました やっちゃうと第三条まできますよ
ということがよくわかる回でした
番組のご意見ご感想こんなテーマで話して欲しいなど ハッシュタグしそふれをつけてぜひXQ Twitterですね
に投稿していただけると嬉しいです それではまた来週さようなら
さようなら