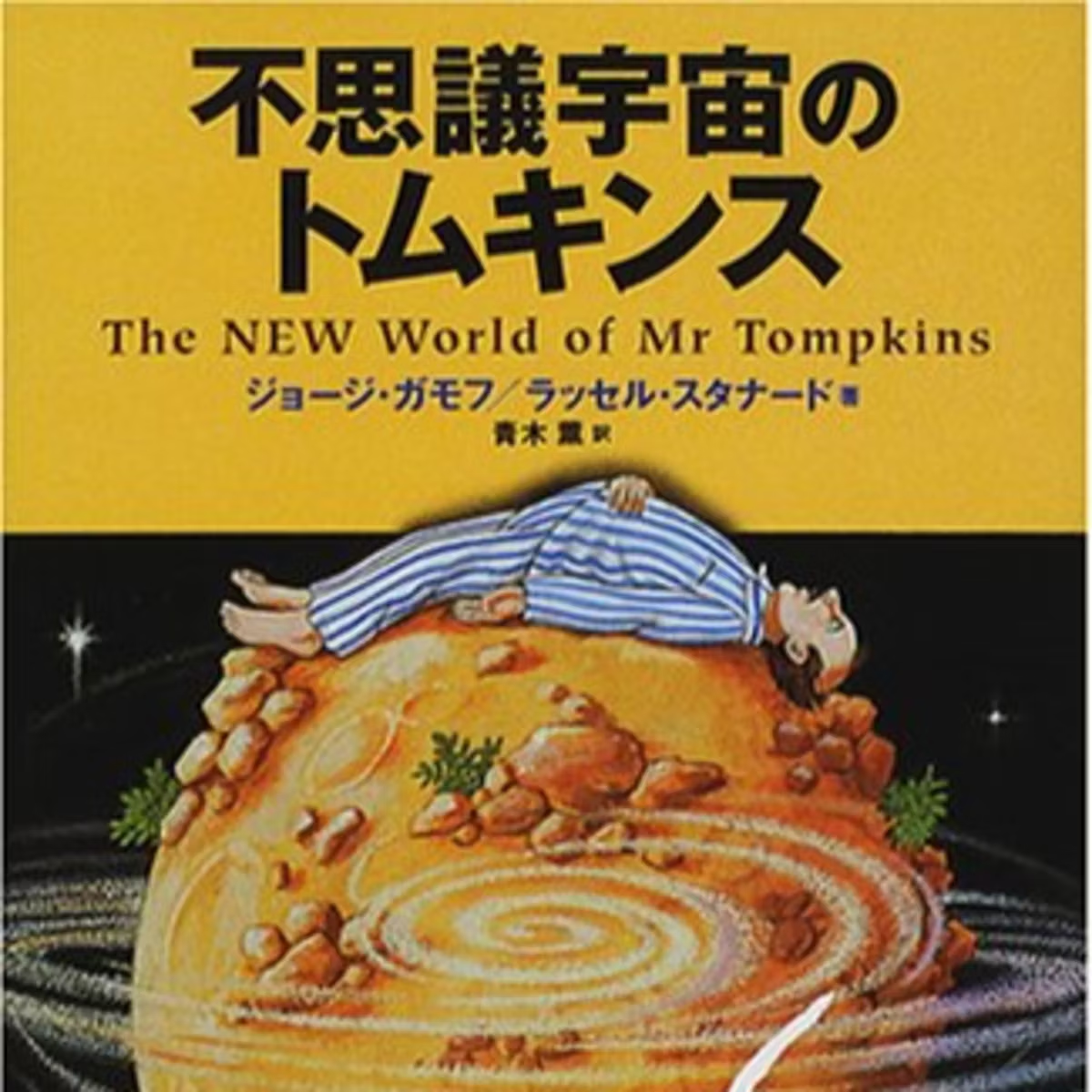00:01
はい、というわけで始まりました。本日はですね、このゴールデンウィーク、この本読もうかなと思っている本の話をしようと思います。
いつもね、何か読んでから話してるんですけど、まだ読んでないんで、読もうかなっていうので一回一つやってみようかなという風に思いました。
今手元に何冊かあって、それを単純に話していくんですけど、一つ目はですね、測りすぎ、なぜパフォーマンス評価は失敗するのかっていう本でですね、これも半分くらい読んだのかな?
読んだんですけど、僕はコンサルの人とかと付き合ってることが最近多いので、その人たちはですね、めちゃくちゃ計測するわけですよね。
いろんな指数をとってですね、比較してみたいなことをめちゃくちゃやるわけですけど、
それのことに関していろいろ疑問があったんですよね。
それで測って何か定式化してもなぁみたいな、結構このラジオでもよく話してましたけど、測って定式化して標準化して、それをPDCを回すみたいなね、どんどん改善していくのだみたいなのが何かを取りこぼすだろうし、
何だろう、何か脆弱性にもつながり得るなと思っているのでですね。
コンサルの人というのはこういうわかりやすいことを示すために、どうしても定量的な計測というのを従うと。
それは必要だからというよりも、正当性があるんだということがわかりやすいから計測をしたいという感じなんですよね。
なんかちょっと主客逆転しているというか、みたいなところがあって、だからですね、本当に話半分に聞いているという感じなんですけど。
さらに言うとですね、じゃあ何でコンサルの人というのが社会で必要とされるのか会社で必要とされるのかというとですね。
僕は専門的なコンサルというんですけど、こういうビジネスに参入したいんだけど、こういう新しい時代に直面しているんだけど、どうすればいいかわからないというのに対してですね。
03:06
そのことをすごく実質している専門的なコンサルの人だったら、すごく使えると思うんですけど、あまりそういうことでもない経営に関するコンサルというんですかね。
経営を客観的に見て、こういうふうなことをやった方がいいんじゃないかみたいなことを言うコンサルは、
やっぱり今回付き合ってみてもそんなに本質的じゃないというか、そもそも経営人がだいたいクライアントなんで、経営人に悪いこと言えないんですよねあまり。
で、まあ程よいことを言うんですよね。で、何だったら経営人が、「ふふふ、わちらの思っていた通りじゃったな。」ってなるのが最高のコンサルの仕事くらいな感じですね。
それにプラス、まあそうですね、思っていた通りです、でもこの辺は少しやってもいいかもしれないですね、みたいなですね、ぐらいな。
でもそんなことってそんなに抜本的なことじゃないんで、別にやってもやらなくてもいいことっていうか、ぐらいなレベルのことなんですよね。
だからまあ本当に、実績というか、影響、最終的な結果だけ見ると大したことではないんですけど、
じゃあ何でそれが必要とされるかというと、やっぱりその権威なんですよね。
このコンサル会社が外部から科学的に計測して、こういうような結論になっている。
何だったら我々経営人と近いことを言っている。だからこれで良いのだ、わかったね君たち、みたいな感じのですね。
外部の権威として存在しているんですよね。
それはなんとなくやっぱり科学進歩みたいなもので、数字で計測してそうやって比較した結果出た結論なんだ、それを有名なコンサル会社の人が言っているんだ、
何だったら聞こうかな、みたいな感じにですね、機能するために存在しているんですよね。
だからほとんど校門様の陰謀みたいな仕事なんですよね。
その陰謀の確かさというか、確からしさ、確かそうに見える感じを担保するためにめっちゃ測るという感じなんですけど、
それがですね、僕にはやっぱり、とはいえ最終的なものが実質的かどうかということにしか現場の僕には興味がないので、
06:02
大した話にはなんねえなと思いながら、こういう感じなんだなと思ってたんですけど、
その時にですね、この「はかりすぎ」という本をですね、見つけたんで、
これはちょっと自分の気になっていることを書いてあるんじゃないかと思って読み始めたんですけど、
読み始めたらですね、今僕がざっくり言ったようなことをですね、ほぼそのままいろんな事例を交えて書いてあって、
逆に言うと何の発見もなかったというか、すごいちゃんとした本なんですけど、面白い本なんですけど、
あまりにも今自分がそもそも思っていたことはそのまま書いてあったんで、
この人なんか大学教授なのかな?で、大学にいてですね、大学改革みたいな中で、
大学がですね、ちゃんとうまく実績を出せているのかというのを国が計測するみたいなことをどんどん強めていったことに対してですね、
すごく嫌だなと思って、こういうことってすごいどこでも起こってるよねみたいなことで、それを調べたみたいな本なんですよね。
でですね、なんですけど、やはりですね、いやなんかこれ測りすぎであまり意味ないんじゃねえの?と思っていたらですね、
測りすぎで意味ないんじゃねえの?という本が置いてあってですね、読んでみたらですね、
僕と同じことを思ったことと同じことが書いてあったみたいな感じで、本当に何の発見もなかったですね。
何の発見もなくないし、こういうですね、自分の今思っていることを強める系読書っていうのがあるなと思うんですよね。
どうなんだろう、なんかこの測りすぎって意味ねえ気がするなと思っていて、
例えば二冊本が置いてあって、測った方がいいっていう本とですね、測りすぎであるって本が置いてあったらですね、
やっぱ測りすぎって本の方が今俺が思っていることと違うことを書いてあるんじゃないかみたいな感じで選ぶと。
そうするとですね、それを読んでやっぱりそうかってまた自分の考えが強化されるって感じで、
ちょっとですね、狭くなっていくような感じもするんですよね。
で、何ですかね、それを破壊してくれるような、今の自分の思い込みみたいなのを破壊してくれるような本っていうのも、
やっぱ常々ちょっと出会いたいなと思っていてですね。
そういう意味で言うとこの本すごいいい本だと思うんですけど、
今の僕にとってはですね、ただただ自分の今の考え方を強化する本でですね、
あんまり読書としてあんまり良い傾向の読書じゃねえなっていう感じはしましたね。
ということでですね、これは最後まで読まないというか、もう読むのやめようかなと思ってるんですけど、
あとですね、二冊目が高鳥屋明さんという人の
09:04
私はアラブの王様たちとどのように付き合っているのかという本でですね、
この人はサラリーマンで中東とかによく行っていてですね、
それで中東に服装とかも完全に合わせてですね、
ものすごく食い込んで行って、走行しているうちにですね、
ものすごいオタクなんですけど、中東のアラブの王様とかにもオタクとかはたくさんいてですね、
すごいアラビア語も喋れて、中東にもちゃんと文化も分かっていて、
かつめちゃくちゃオタクって詳しい奴がいるっていうんで、
いろんな王子とかに呼ばれてですね、どんどん食い込んで行った人で、
アラブで一番有名な日本人と呼ばれてるんですけど、
まあちょっとその人の本を読んでみようかなと思いましたね。
でですね、あとは、これ何だっけ、
創始の本か、創始、鶏となって時を告げよっていうですね、
中島孝博さんって人の創始の解説の本ですね。
中島孝博さんは前に話した、道徳を築き続けるを翻訳してた方かな、東大の教授かなんかなんですよね。
でちょっとね、創始、老創始祖って、
簡単な解説書くらいだったら読んだことあると思うんですけど、
創始はですね、かなり老子がすごく短い言葉で、
ズバッズバッズバッって本質しか言ってませんみたいな感じと比べると、
創始はすごいエピソード豊かにそういう話をですね、
老創始祖とかいうぐらいなんで、創始にも通じるような思想をそのものの言葉で語るんじゃなくて、
エピソードを通して感じ取らせるみたいな感じですね。
とにかくエピソード豊富、創始ってすごい分厚い本なんですけど、
でですね、ちょっと興味はあったんですが、
あんまり創始の本もちゃんと読んでなかったなと思ったんで、
面白そうだなと思って借りてきました。
でですね、次が、
ジー・ガモフっていう人のですね、トムキンスの冒険っていう本ですね。
これ結構昔の本なんですけど、
これはですね、
がっくりと言うと、トムキンスっていう人が、
このガモフっていう人は物理学者なんですよね。
物理学者で量子力学とかがですね、どうしてもうまく説明するのが難しいという中で、
この人すごい物語の才能もあって、
12:03
量子力学の世界をですね、分かりやすく伝えるために、
トムキンスっていう主人公が、
不思議の国に迷い込むみたいなストーリー仕立てでですね、
量子力学を解説していると。
その手法がですね、
量子力学って、
僕らの普通の感覚、量子力学とか相対性理論って、
普通の感覚だと理解し難いようなですね、
感覚とすごいずれているようなことが起こるわけですけど、
じゃあなんでそれが起こるのかっていうと、
僕らの感覚って、
自分たちの体の大きさとかですね、
そういうものに基づいた常識、
その周囲から形成された常識でできているので、
例えば僕の身長が1光年仮にあったとしたら、
めっちゃ相対性理論とかはですね、
理解できると思うんですよね。
相対してるねみたいな感じで、
感覚的に理解できると思うし、
逆にですね、自分の体の大きさが一原子レベルぐらいの大きさだったとしたら、
ああ、量子力学してるねみたいな感じでですね、
理解できると。
例えばちょっと面白い例えで、
誰かが言ってて、なるほどって思ったんですけど、
かたつむりですよね。
かたつむりがあれぐらいのスピードで動いていると。
あれぐらいのスピードで動いているから、
音が、例えばスピーカーから大きな音楽が流れています。
かたつむりがその前を張っています。
で、そのスピーカーの音が遠くに行ったら小さくなるっていうのは、
かたつむりからすると想像がつかないだろうと。
そんなですね、音が、
例えば音が鳴っているスピーカーからどんどん走って遠ざかっていったら、
それに合わせて音って小さくなっていくわけですけど、
かたつむりはですね、かたつむりのスピードでいくらスピーカーから離れていってもですね、
音が小さくなるって体感できないと思うんですよね。
なので、そういうですね、やっぱり自分の体の大きさとかですね、
そういうものによって体感というのがですね、規定されていて、
その規定の常識の中で考えると、
世界の在り方っていうのがですね、すげえ不思議に見えると。
不思議に見えて理解しがたいものに見えるんですけど、
じゃあかたつむりをですね、人間の足の速さぐらいにしてみれば、
確かに音って小さくなるわ、みたいなことが実感できる。
そういうようなですね、手法でこの不思議の国に入ったトム・キンセさんはですね、
量子力学とか相対性理論の不思議さっていうのを実感できるような、
15:03
いろんなスケールとかで作られた世界の中に迷い込んでいくみたいな、確かそういう話なんですよね。
これまた面白そうやなと思いまして、
この辺をゴールデンウィークに思うかなと思っております。
というわけで本日は以上です。ありがとうございました。