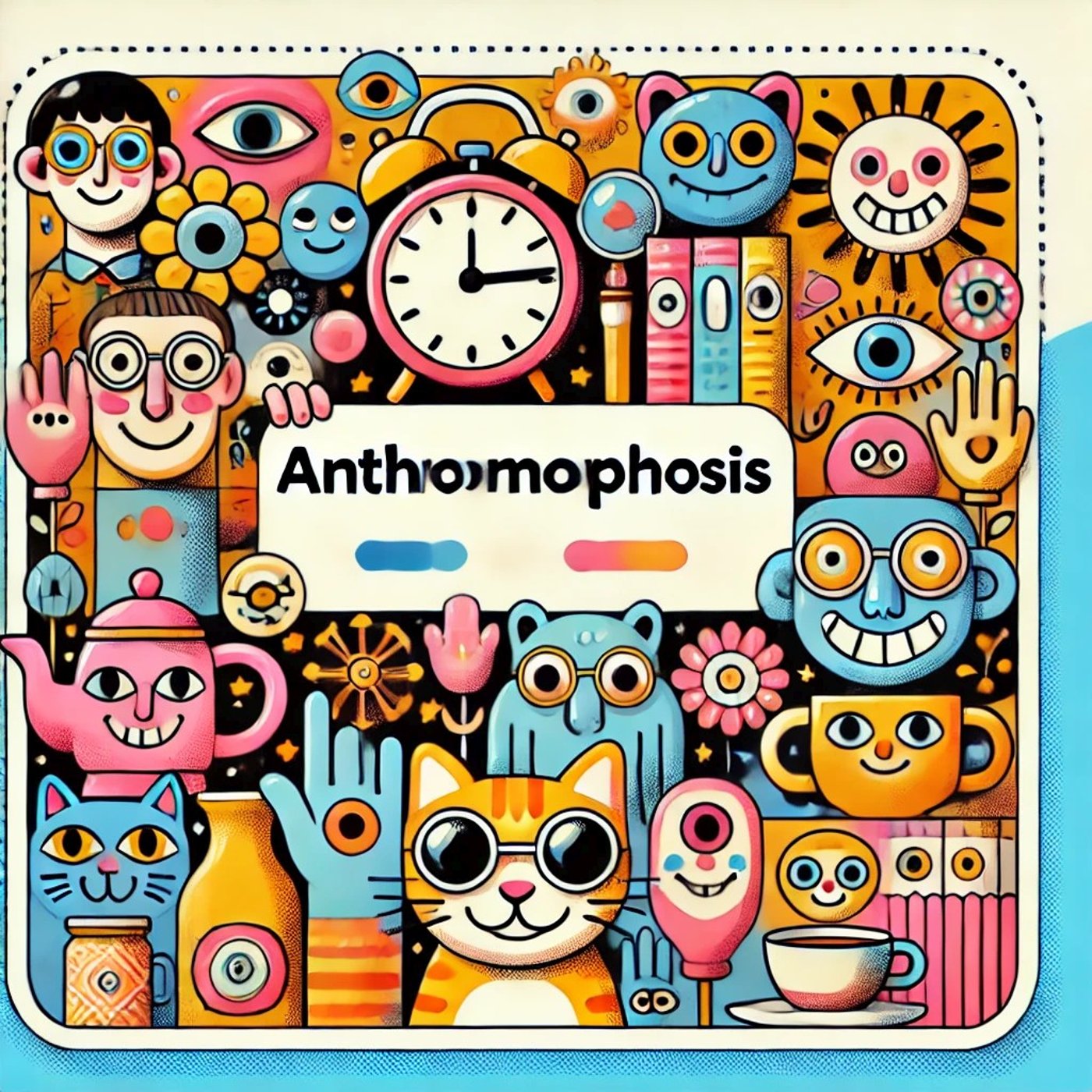00:03
おはようございます。英語の歴史を研究しています。慶應義塾大学の堀田隆一です。
このチャンネルでは、英語の先生もネイティブスピーカーも、辞書も答えてくれなかった英語に関する素朴な疑問に、英語史の観点からお答えしていきます。
毎朝6時更新です。ぜひフォローして、新しい英語の見方を養っていただければと思います。
今回取り上げる話題は、英語は文法的性がないからこそ擬人法が生きてくる、という話題です。
現代の英語というのは、ご存知の通りですね、近隣のヨーロッパの諸言語と異なって、文法的な性、グラマティカルジェンダーというものがない言い訳ですね。
その他のヨーロッパの言語、フランス語であるとか、ドイツ語であるとか、ロシア語であるとかですね、こういった言語には名詞ごとに性が割り振られている。
例えばドイツ語で言えば、男性名詞、女性名詞、中性名詞というふうに割り振られているわけですね。
こういったものが英語の場合はない。このまま現代英語の特徴、性がない、文法性がないという特徴はですね、学ぶ上では非常に楽で良いということになります。
千年遡った古英語の時代にはちゃんとあったんですね。同じゲルマン系の言語ですから、今のドイツ語と同じ形で男性名詞、女性名詞、中性名詞というふうに分かれていて、
単語、名詞ですけれども、名詞によって全て割り振られていたということなんですね。それが次の中英語の時代になってですね、なくなっていきます。
どうして英語で文法性がなくなったかというのは、これ自体がですね、大きな英語史上のテーマなんですけれども、簡単に言うとですね、語尾がどんどん弱まってしまって、
語尾によって性であるとか、その他の格なんかもそうなんですが、いろいろと区別がつかない言語になってしまったということなんですね。
こういった事情でですね、近隣のヨーロッパの諸言語と比べると比較的珍しいことにですね、文法性を失った言語ということになったわけです。
変わって現れたのが、文法的な性ではなくて、単にそれが指しているものが男だから男性、例えばひいで受けるとか、女だからしいで受ける、どっちでもないものだからいっとで受けるという非常に単純なですね、文法的でない性、これは自然性、ナチュラルジェンダーと言っていますが、つまり当然でしょうという性ですね。
あるいは生物学的という取り方をしてもいいと思うんですが、このナチュラルですね、グラマティカルに対してナチュラルな性というものになって、そして現代に至るわけですね。
03:02
そうすると、文法性がなくなったこの中英語以降ですね、英語では基本的に男だったらひい、女だったらしい、それ以外のものですね、無生物のものだったらいっとという現代にまで続く原則が出来上がるんですが、
とはいえですね、いわゆる擬人性というのがありますね。いわゆる擬人法なんですけれども、人ではないものですね、無生物であるもの、普通だったらこれいっとで受けるということなんですが、それを擬人化して男であるとか女であるとかみなすという、これは現代の詩であるとかレトリックでもあると思うんですが、
こういったものは中英語以降ですね、出てくるわけですね。これは従来の文法性とは全くリンクがありません。全く別の、いわばレトリックとしての擬人性ということで、別軸で中英語以降これが始まるわけですよね。
例えばですね、中英語の文学なんかを読んでいますと、moonですね。これ月ということなんですが、これが女性名詞で受けられるようになるということですね。これ本来の古英語ではですね、当時の文法性としては、実は男性名詞なんです。
ところが中英語になって、いわゆる擬人性ですね。擬人化されたものとして見る場合には女性として受けられたと。これは何でかというと、いわば神話とか伝説、古典ですね、の影響で伝統的にですね、女性で受けてきたということが、つまり英語国以外でですね、あるわけです。ギリシャ神話とかローマ神話とかですね。
他にlove、愛ですよね。これはエロスとかキューピッドっていうことなので、これ男性として擬人化されています。それからwar、戦争ですね。これは戦いの神マルスということで、これ男性とされるというような形でですね。
いわゆる大陸の神話伝説、古典などの影響によって、改めて擬人的に性が割り振られたということで、大抵これ、古英語時代の文法性とはずれていることから分かる通りですね。そこからの直接のリンクはないっていうことです。
その古英語からの語源的、語詞的な影響はないと言いましたが、ラテン語であるとかフランス語でですね、これらの言語では文法性ありますから、その影響で英語での使用の際も男性名詞とか女性名詞であるかのように受けるという、こういう意味での語源、語詞的影響はあります。
例えばローム、ローマですね。これはラテン語の女性名詞ローマから来ているので、英語でも中英語以降ですね、ロームと来たらこれをCで受けるというようなことはあったりするわけですよね。
06:11
他に例えば長所微転ですね。これは本来フランス語の単語です。女性名詞を借り受けたものですので、それに従って英語に入ってきても、やはり女性名詞として扱われるような、こんな外国語の影響っていうのはありますね。
それから3つ目にはですね、心理的影響とか主観的印象といっても良いようなもので、いわばその対象がですね、雄大だったり強烈だったりすると、男性に見立ててみたり、優美だったり、可憐なもの、他産なものを女性とするっていうような、これが我々にとってもイメージしやすい。
いわば心理的、主観的な個性の付与っていうんですよね。これはあったりするわけです。
例えば、wind, ocean, summer, anger, death なんていうのは、これは男性的なイメージを乗り移らせて、男性名詞であるかのように扱うであるとか、逆に女性名詞としては、nature, spring, art, night, wisdom のようなものが主流語以降ですね。
女性の擬人性を割り当てられてきたというものがあります。ただ、この心理的影響ということですが、ある意味主観的だったり任意だったりしますよね。
なので、ある程度傾向があったとしても、実は書き手によって同じ単語について、ある書き手は男性名詞として扱うものを、別の作家は女性名詞として扱ったり、同じ作家の中でも揺れていたりとかですね。
いろいろな事情があって、一貫してないというものもよく見られるんですね。他には、同じ中英語記でも、前半と後半とで、擬人性の付与が変わったり、例えば先ほど、death っていうのは男性的なものということで、男性名詞とみなすというような雰囲気があったんですが、これは中英語の前半のことで、後半になってくると、
これがですね、おそらくラテン語、フランス語の形ですね、文法性に惹かれるという形で、女性名詞っぽく、女性の擬人性を与えられるというようなことも起こったりして、なかなか一筋縄ではいかない、簡単には説明できないような状況になってきます。
ただ、このように心理的影響とか主観的感情としてあげた三つ目のものですね。ある意味、その時々のイメージで男性にしたり女性にしたりできるという特徴は、実はよく考えてみると、これ英語の特徴なんです。
09:16
つまり、文法性を失ったからこそできる芸当なんですね。文法性が残っていると、フランス語なりドイツ語なりラテン語なりですが、どうしても最初に決まってしまっていますので、それと逆の性をですね、例えば擬人性とはいえ、逆の性を割り当ててしまうと、どうもしっくりこない。チグハグになってしまう。
こういう感覚がないのがある意味英語なんです。その時々のイメージでどちらの個性にも割り振られるというようなこと、それは英語に文法的性がないからこそなんですね。ということで英語は文法的性がないからこそ、擬人法が生きてくるという面白い言語なんです。ではまた。