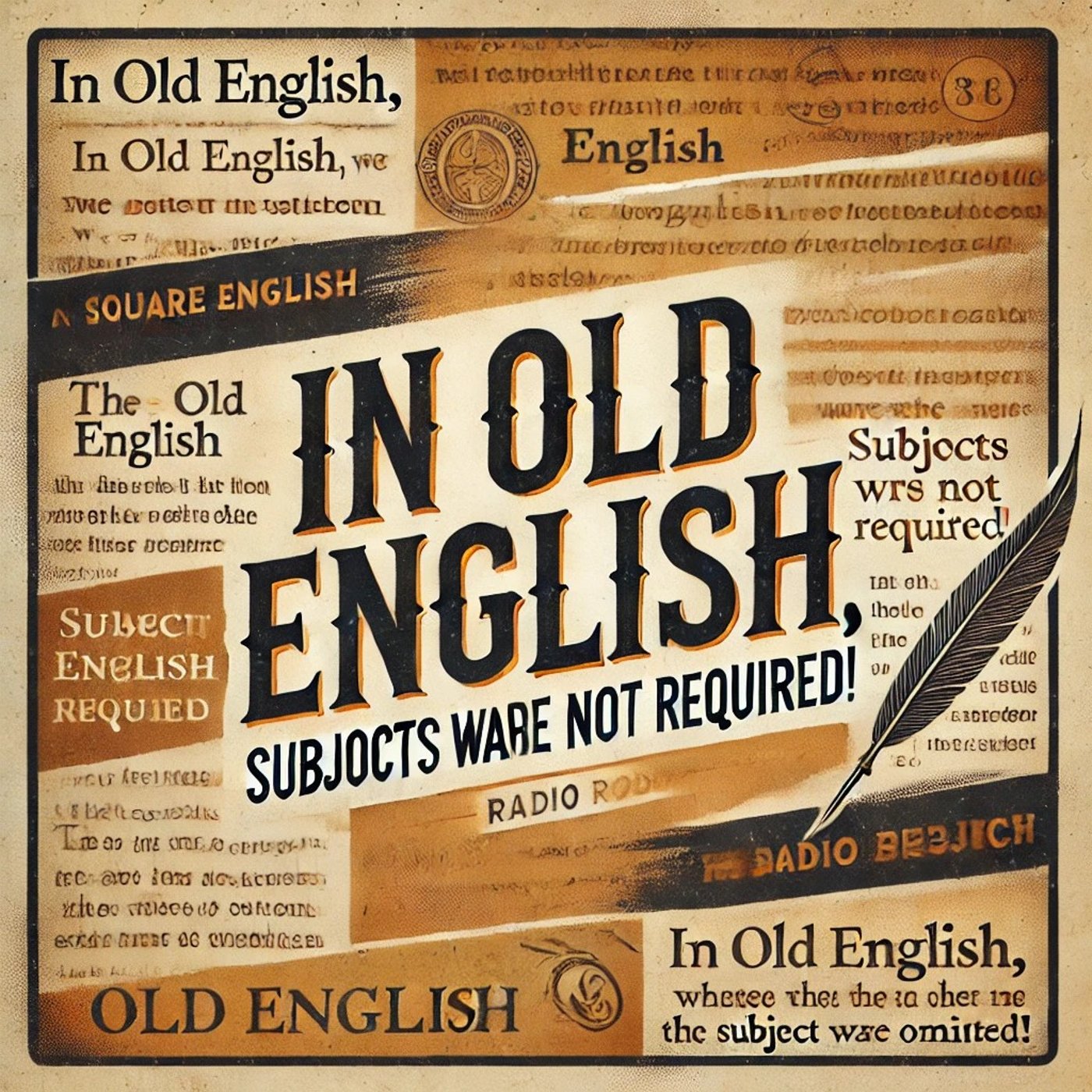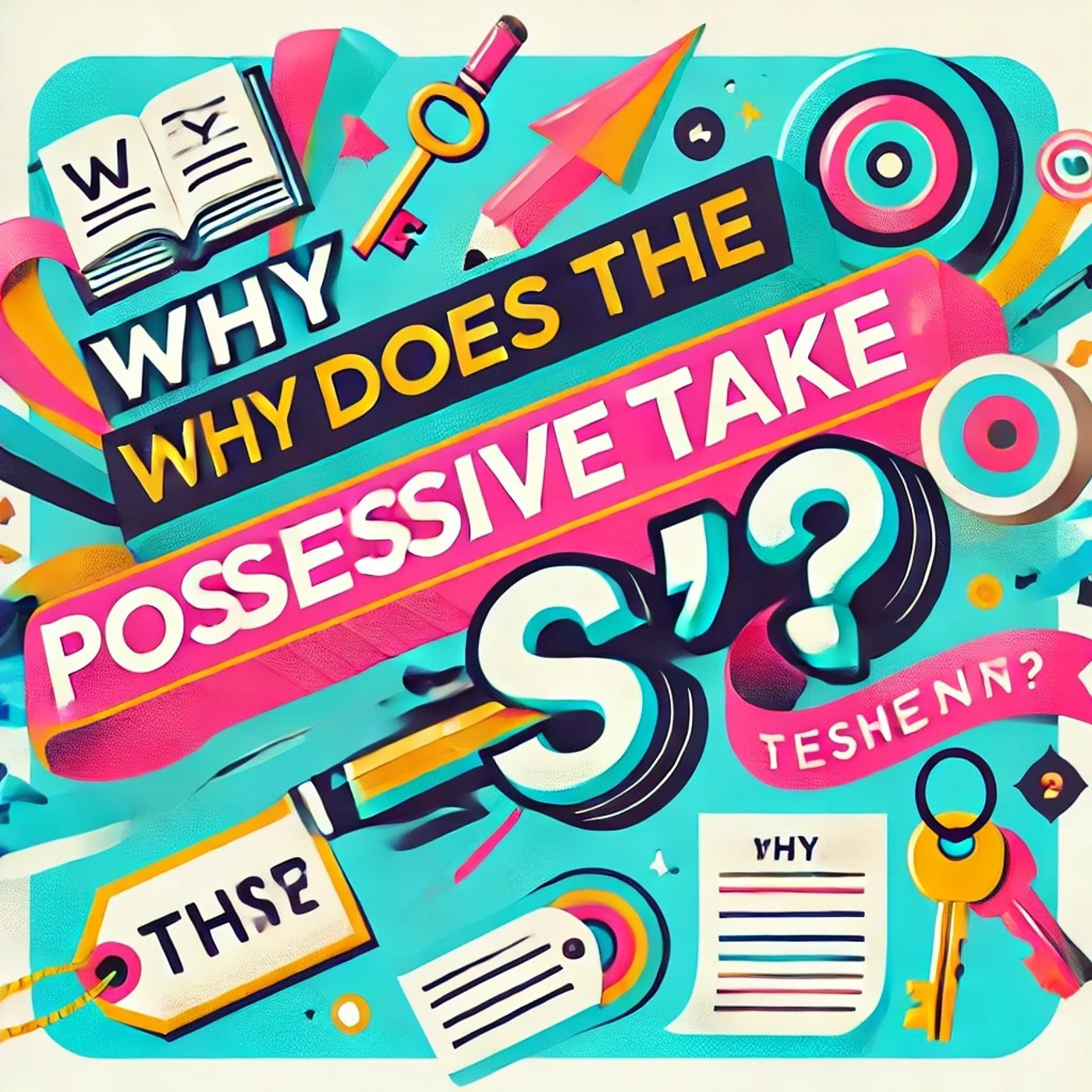00:01
おはようございます。英語の歴史を研究しています。慶応義塾大学の堀田隆一です。
このチャンネルでは、英語の先生もネイティブスピーカーも辞書も答えてくれなかった英語に関する素朴な疑問に、英語史の観点からお答えしていきます。
毎朝6時更新です。ぜひフォローして、新しい英語の見方を養っていただければと思います。
今回取り上げる話題は、it の所有格 its は実は歴史が浅い、という話題です。
この認証代名詞の体系というのは、唱えて暗記して覚えるわけですよね。
I, my, me, mine, you, your, you, yours ってやつですね。
そして三認証になりますと、これが he, his, him, his そして she, her, hers そして三認証の中でも中性と言いますかね。
無生物のものに使われるこの it が it, its, it となります。
この四つ目の所有代名詞、それのものという使い方は原則としてない。
つまり代名詞の体系は表になるわけなんですが、あの部分だけがですね、罰がついてるっていう感じなんですね。
主格は it ですね、主語の形。それから目的格、これも同じ it となっているんですが、
その所有格にですね、この its と ITS と綴る形がありますね。
これは使う頻度としてはですね、他の認証代名詞の所有格なんかに比べれば比較的少ないかもしれませんが、
そこそこ使われるわけですよね。例文としては例えばですね、
Their house has its own swimming pool. であるとか、
The company increased its profits. とか、
The project is entering its final stages. のように、そこそこ使われますよね。
この its に今日は注目したいと思います。
さて、タイトルでも述べましたように、この its 所有格の its というのは歴史が3位ですね。
せいぜい16世紀くらいからということで、400年プラスというほどの歴史なんですね。
それ以前、古英語、中英語の時代には、実はですね、it の所有格は his だったんです。
つまり、男性代名詞 his と、全く同じ形の所有格 his というのを使ったんですね。
これはですね、区別がつかないではないかといえば、確かにそうなんです。
古英語の時代にはですね、文法的な性というのがありまして、中性名詞、男性名詞、女性名詞とあったわけですが、
この代名詞においてはですね、男性と中性というのは、いろいろと似ているところがあってですね、
この his、古英語の場合は his と発音したんですが、これで所有格を表したということなんです。
03:07
ですから、受けるものは男性名詞の場合と中性名詞の場合があった。
こういうふうに男性と中性が一致してしまっているというのは、実は所有格だけではなくてですね、
やはり古英語、中英語では目的格の中でも特に何々にという、いわゆる間接目的語になる格ですね。
当時は予格というふうに、文法用語ではいうわけなんですが、与える格ですね。
何々にという格、これも実はひいの場合といとの場合とで、共通してひむなんです。
つまり、所有格だけではなくて、この間接目的語の格ですね、これもひむというふうに一致していたということです。
なので、男性名詞と中性名詞がいろんなところで形が融合してしまうというのは、古英語の時代には珍しくなかった。
そしてそのまま中英語にもおよそ受け継がれたんですね。
なので文脈上ですね、ひすとかひむって出ると、これはそれなのか彼なのかというのは文脈上を判断しないといけないということになりますね。
形だけでは分からないということです。
ところがですね、中英語の終わり、そして近代語記にかけてですね、この状況が少し変わってきて、そして現代風になっていきます。
中英語記にはすでに文法的な性というのは廃れていたんですね。
そして、物なり人なりを見てですね、これが男性であれば男性で受ける、非で受ける。
女性であれば非で受ける。そうじゃない、一般の物であれば一等で受けるというような当然の、今我々が当然視しているような自然性というものになってきますね。
そうするとですね、男性と中性が一致している形がね、ひすとかひむみたいな。
というのは、小英語ではまだ良かったんですけれども、発想がですね、自然性、実際の生き物の性と強く結びつけられるようになるとですね、やはり違和感が生じていくと。
そこで、例えば目的格のひむなんかもですね、その一等に対応するひむっていうのは消えていって、代わりにですね、一等はそのまま主格と同じ一等が目的格としても使われるようになっていったと。
こうしてひむと一等が男性、中性の間で分かれてくるわけですね。
この区別するという流れがいよいよ、所有格にもやってきました。
これまでは、hisと言っていれば、これはhe、it両方の所有格だったんですが、これが馴染まない感覚になってきたんですね。
すると、新しいですね、一等に対応する所有格っていうのを作らなければいけなくなる。
hisの方は男性の方に取られてですね。
で、itはどうするかといったときに、いくつか対処法ってのがあったんですね。
06:05
一つはですね、そのままitで使っちゃうと。
つまりこれ、主格も目的格も所有格もなくですね、とにかくitで所有格として使ってしまう。
これ実は結構あったんです。
近代語になってもこれは使われているくらいですね。
それから、of itという言い方で逃げようと。
2語を使ってですね、後ろからof itのようにかけていくってやり方。
それから、thereofなんてのもありますね。
これもof itぐらいの意味なんですが、thereofという形で、
itの所有格あるいは所有格の代用としようというような、こんなものが生まれてきたんですが、
少し後半になってですね、現れてきたのが、実はitなんですね。itsです。
これ発想はすこぶる簡単で、要するに名詞を作るときの所有格。
john's houseというときのあのsですね。
あれは今でapostrophe sをつけるわけですが、
これを名詞ではなく代名詞にまで応用してしまおうというすごいことが起こって、これitsが生まれたんですね。
そして、名詞の場合にはapostrophe sと今なっていると言いましたが、
実は同じように、この所有格のitsも、つまりit'sという綴りも普通にあったと。
これ現在、apostropheつけてしまうと、it isの省略形としてのits。
あるいは、it hasですかね。の省略形としてのitsなわけですが、
実はこれ出始めた当初は、むしろit'sこれで所有格として使うほうが、
多かったぐらいなんですね。
このitsという所有格の形が現れるのは、16世紀の後半でですね。
当時はおそらく新しい表現ですから、しかも非常に単純な発想ですよね。
itにsをつけて所有格なんていうのはですね。
口語的な少し軽い響きを持っていたのではないかと思われるんですね。
その証拠に16世紀後半のシェイクスピアですね。
では基本的に生存中のテキストでは、このitsというのは一切現れていません。
先ほど述べたようなsがつかない、itですね。
つまり主格目的格と同じ形で所有格として使うというほうが、
むしろシェイクスピアでは普通でした。
ただ有名なファーストフォリオ、1623年に出版されたファーストフォリオなんかでは、
itsというのが1例現れています。
アポストロフィーなしで。
アポストロフィーありのものが9例現れていますので、
ちょうどこのぐらいの時期、1600年を境ぐらいにして、
少しずつ普及してきたものではないかと。
09:04
ほぼ同じ時期に出たですね、1611年のauthorized versionと呼ばれる聖書ですね。
聖書は固い言葉を好みますので、
当時まだ軽くて交互的だったitsなんてものは基本的に出ていません。
このように、交互的な雰囲気で出てきたものが、
17世紀を通じてかなり一般化してきて、
そして現代、普通に使われるようになっているんですが、
綴りに関する限りですね、このアポストロフィーあるバージョンとないバージョン、
結構これ揺れながら続いたんですね。
実際アポストロフィーあるバージョンは19世紀初めまで続いていたぐらいで、
こんな変な代名詞を紹介しました。
それではまた。